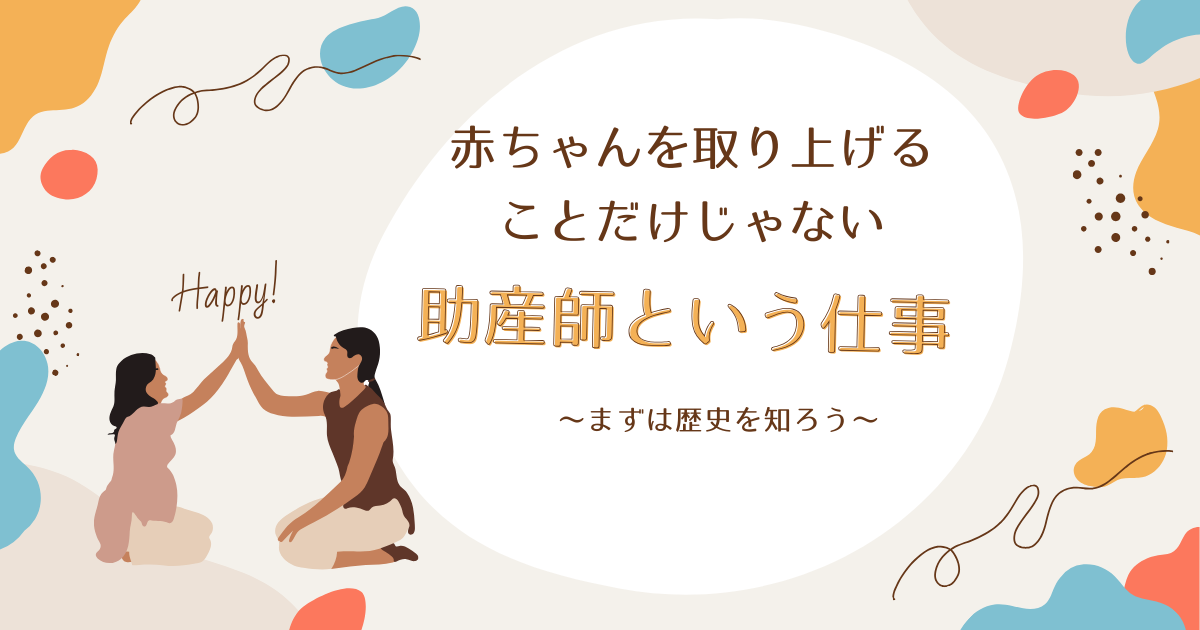
助産とは?
助産の概念の神髄は・・・
出産時の支援を中核とした次世代の健全育成を目的としていることは論をまたない。
しかし、保健・医療・福祉の考え方やあり方および女性や子どもの社会的地位などが、
時代の社会的背景によって変化していることに伴い、助産の概念や内容なども時代の推移を反映し変化してきた。
助産の起源
助産=「出産をたすける行為」は人間に特徴的であるとされている。
陣痛のはじまった産婦に付き添って産婦を励まし慰めてその苦痛をやわらげ、生まれた子どもの臍の緒を切り、後産の始末を行い産婦の世話と出産時の処置を行うなど、助産とは産婦に付き添うことであったと考えられる。
子どもを産むこと、子どもが生まれること、子どもを育てること、子どもが育つことの意味は、国や地域社会、家族、夫婦、個々人によって異なる。
助産とは広辞苑によると
「分娩(妊婦検診や胎盤娩出など)を助け、産婦や新生児の世話をすること」を意味する。
平安時代は「腰抱」安土桃山時代は「取上婆」と呼ばれていた。
第二次世界大戦後、助産を取り扱うものの名称が「産婆」から「助産婦」に変更された。
助産師に求められることは、助産を実践し、専門職としての責任と職務を担い、妊娠前の時期から更年期、人生の終末までを通じたリプロダクティブライフサイクルにある女性や新生児の健康と生活の質を維持・向上させることである。
また、助産師は、助産の実践において、妊娠・出産が正常な生理学的プロセスであること、女性やその家族、地域にとって重要な意味を持つ経験であることを十分に理解し、女性の人権やリプロダクティブヘルス・ライツを保護・支持し、継続的なケアを科学的根拠に基づき提供することが求められる。
★助産師の声明
「助産師とは」
これらのケアには予防的措置や異常の早期発見、医学的措置を得ることなど、必要に応じた救急処置の実施が含まれる。
法に定められた所定の過程を修了し、助産師国家試験に合格して、助産師籍に登録し、業務に従事するための免許を法的に取得した者である。
助産師は、女性の妊娠、分娩、産褥の各期において、自らの専門的な判断と技術に基づき必要なケアを行う。
さらに、助産師は母子のみならず、女性の生涯における性と生殖にかかわる健康相談や教育活動を通して家族や地域社会に広く貢献する
その活動は育児やウイメンズ・ヘルスケア活動を包含する。
助産師は、病院、診療所、助産所、市町村保健センター、自宅、教育、研究機関、行政機関、母子福祉施設、その他の助産業務を必要とするサービスの場で業務を必要とするサービスの場で業務を行うことができる。
1生命の尊重
2自然性の尊重
3智の尊重
「基本的助産業務に必要な能力」は、妊婦と家族のヘルスケアニーズの変化に応じるために2010年に改訂され、そのなかで、助産の基本概念と助産師が備えるべき能力として、7つの知識・技術・能力の具体的な内容が示されている。
我が国における助産の定義
助産とは「妊産婦の主体性を重んじた安全安楽な出産の援助を頂点に、人間の生涯を通した生殖や性に関わる保健活動である。
助産意義・本質
◆助産は母子及びその家族に対する人間性、自律性、個別性および社会・文化的側面を重視した支援を通して、親子関係・家族関係のよりよい形成や発達を促し、次世代の健全な育成に寄与する
◆助産は女性の生涯を通しての性や生殖にかかわる健康生活の援助に独自の機能を果たし、女性と家族の健康生活の質的向上に寄与する
出産の変遷
出産の変遷は出産の「施設化」と「医療化」
治療すべき病気として医療管理のもとに組み込まれていくことである。
現在の出産において、妊産褥婦のニーズの多様化に伴い、安全性と安楽性・満足度の両価値を実現するために、妊産褥婦を中心に据えた医師と助産師との連携・協働による、自然性の尊重と医学的援助の融合が求められている。
◎出産の施設化
自宅出産の割合は1950年(昭和25年)95%
施設分娩に99%移行したのは1975年(昭和50年)
今日では99.9%施設内分娩
出産の施設化は、異常の早期発見・早期治療による周産期死亡の減少をもたらした一方で人間の誕生の心理的・文化的・社会的意味をそぎ落としてしまい母性意識の発達や子どもの心身の発達に多くの負の影響を生じるようになった
◎出産の医療化
1960年代には帝王切開・吸引・鉗子分娩、会陰切開、陣痛促進剤、麻酔などは広く実施されるようになり、1970年代以降は超音波診断装置、心音計などの科学技術が出産ケアに導入
◎自然性の尊重と医学的援助の融合
1980年代に入るとケアの受けてである女性たちから、出産に対する医療技術の介入や、医療者中心の画一的なケアに対する抗議が提唱されるようになる。
1990年代に入ると妊娠・出産に対するケアは産婦中心のケアへと大きく転換することとなり、産婦自身による主体的で満足のいく出産を取り戻そうとする動きがみられるようになってきた。
最近では晩婚化・晩産化の進行に伴うハイリスク妊娠・分娩の増加
少子化の進行や体外受精児の増加
育児知識の伝承や育児支援ネットワークの脆弱化と児童虐待の増加など、妊産褥婦のニーズが多様化し、妊娠・出産・育児に伴うさまざまな現象と価値観が錯綜している。
現在の出産においては、自然性の尊重と医学的援助の融合により、産婦や家族が医療の進歩を享受しつつ、産婦が望む安全性および安楽性・満足度の両立を実現するために産婦自身が寄り添い、支援することが助産師をはじめとする医療従事者に求められている。
SBAとTBAの違い
分娩介助者(SBA)とは
助産師や看護師、医師などのように公的に認定された保健医療専門家であり、正常妊娠ケア、正常分娩ケア、出産直後のケア、母児に合併症が生じた場合の搬送に関して熟達するために教育と訓練を受けたものをいう。
伝統的産婆(TBA)とは
出産時に産婦に付き添う女性で、経験によって出産介助技術を身につけている者であり、地域での妊娠期から産褥期のケア提供者である。
一般的に高齢で、既婚で出産経験があるものが多く、現地語や地域の伝統や慣習を周知していることからも、人々からの信頼はあつい。

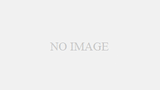
コメント